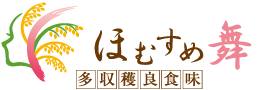ほむすめ舞とは
平成25年に誕生。
≪多収穫でありながら良食味≫
の特性を持つ新品種

「ほむすめ舞」多収穫でありながら良食味という特徴を生かし、作り手(生産者)と買い手(米穀取扱業)
ならびに消費者にとって「三方良し」の関係性作りを目指します。
世界に誇れる農業技術を維持し続け「三方良し」の心得で米農業界は盛り上げ、
若い人たち夢の持てる業界になれば、
日本の美称「瑞穂の国」を世界に誇り続けるための力になると考えています。

品種の成り立ち
来 歴
- 平成16年「夢ごこち」×「ふくひびき」の交配
- 平成17年冬季F1の養成
- 平成17年夏季F2の集団栽培
- 平成18年冬季F3の集団栽培
- 平成18年夏季F4集団栽培および個体選抜
- 平成19年以降選抜系統の選抜群栽培
- 平成25年2月26日「ほむすめ舞」の名称で品種登録の申請
- 平成28年3月7日種苗法による品種登録番号 第24853号
名前の由来

みずみずしい稲穂が、多く取れることから瑞穂のの実る国=「瑞穂国」と言われて来ました。
みずみずしい稲穂を見る生産者の気持ちは、まさに嫁入り前の「むすめ」と同じです。
多収穫で極良食味の特徴通り、実りの秋には、田んぼ全体が今まで見たことのない黄金色で埋め尽くされ、「たくさんの娘が舞い踊っている」ように見える事から名前を「ほむすめ舞」と名前を付けました。
ほむすめ舞の普及
弊社が平成26年に育成者権を取得して以降、これまで18の府県で生産をしています。
作り手の生産者様・パートナー企業様に支えられ総面積は全国併せて約200ha以上の作付をするに至りました。
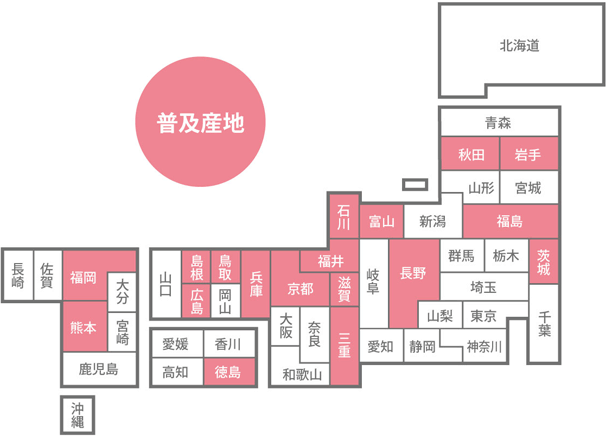
ほむすめ舞はこんな生産者様のニーズに
お応えする品種です
- 1品種の作付が多すぎて収穫作業が
集中してしまう… - 米の収穫後は野菜を作付する為、
早く米の作業を終わらしたい… - 収量のいい品種を作付したいが
晩生品種は作付できない… - 倒伏しにくい品種を
作付したい… - 新しい品種を作りたいが販売先が
無いのが心配…
「ほむすめ舞」は早生系の多収性品種です。適期分散や収量UPによる増収入を目的に取り組まれている生産者様にはピッタリ。
「ほむすめ舞」は稈長・穂長併せても約100cmの短稈品種です。
「ほむすめ舞」は生産各県にパートナー企業がいるので収穫玄米の集荷・販売についてお悩みの場合は、パートナーをご紹介可能です。
品種の特徴
「ほむすめ舞」は早生系の多収穫品種です。育成地における成熟期は「あきたこまち」「ひとめぼれ」とほぼ同等の偏穂重型・早生系品種の位置付けです。
生育期モデル事例
| 平 場 | 山間部 | |
|---|---|---|
| 移植期 | 4月末~5月初旬 | 5月初旬~5月中旬 |
| 出穂期 | 7月中旬~7月末 | 8月初旬~8月中旬 |
| 成熟期 | 8月中旬~8月末 | 9月中旬~9月末 |
品種の特徴
- やや短稈で稈質良く、耐倒伏性は強
- アミロース含量が低く、軟らかくて程良い粘りの極良食味
- 分ケツはコシヒカリに比べて少ない
- 葉いもち病:「極強」(基本防除は必要)
- 葉色は普通、止葉はやや立つ
- 穂発芽性:「難」
- 粒着はやや密(品質劣化に注意)
生産ポイント・施肥モデル
生産ポイント
-
育苗期
3月末~4月末
- 種子の浸漬時においては水温は10~15℃で10~7日実施します。一般品種よりも+20℃(+1日)の積算温度で120℃が目安です。
-
移植期
4月末~5月中旬
- コシヒカリに比べ分けつが少ないので穂数・籾数の確保が肝要になります。当社では有効茎数を確保する為にも栽植密度は20株/m2(60株植)程度を推奨しています。
-
分けつ期
5月中旬~6月末
- 初期生育を良好にして良質茎を確保することが肝要となります。
目 標 ≪ 良質茎:18本/株 → 360本/m2の確保 ≫ -
穂ばらみ期/出穂期
6月末~7月末
- 茎数確保後中干しを行い、後半の稲の活力を高めましょう。栽植密度が高い圃場は紋枯れ病に注意です。穂肥は出穂23日前が適期です。幼穂3mm~5mmが適当なタイミングとなります。ほむすめ舞は短稈品種の為、コシヒカリの穂肥よりも早い段階のタイミングでもOKです。
-
登熟期
7月末~8月末
- 成熟期予測:積算温度1,000度として平均気温25度と仮定すると成熟日数を35日〜40日間を想定しています。
時 期
ポイント
施肥モデル
- 分肥型:5~7kg/N(元肥) 2~3kg/N(穂肥)
- 一発型:10kg/N